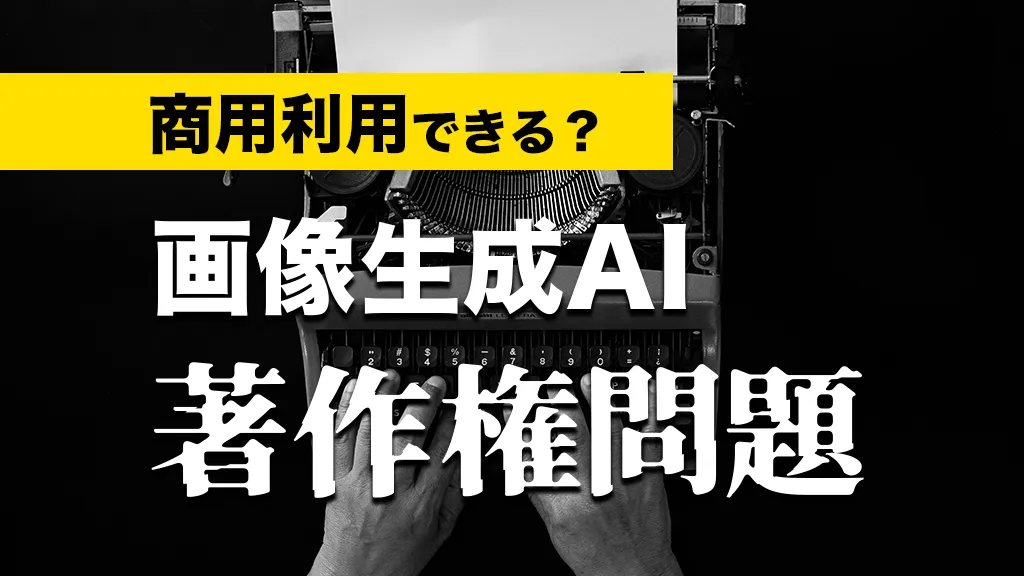
知らないと危険!画像生成AIの著作権問題と安全に使うための5つの対策
画像生成AIで作ったイラストや写真をSNSや商用利用に使っても大丈夫?
近年、MidjourneyやAdobe Fireflyといった画像生成AIが急速に普及し、個人でも手軽に高品質な画像を作れるようになりました。
しかし、「著作権はどうなるの?」「勝手に使うと違法では?」と不安を感じる人も少なくありません。
結論から言うと、商用利用はツールの利用規約に従っていれば使用可能です。
ただし、学習データに他人の著作物が含まれていたり、既存作品を模倣するプロンプトを使った場合には、著作権侵害と判断されるリスクもあります。
本記事では、文化庁の公式見解や海外の判例をもとに、画像生成AIを安全に使うためのルールと注意点をわかりやすく解説します。
画像生成AIとは?
画像生成AIとは、テキストや指示文から自動的に画像を生成するAI技術のことです。
近年は、誰でも短いプロンプトを入力するだけで高品質なビジュアルを作れるようになり、デザイン・広告・SNS運用など幅広い分野で活用が進んでいます。
特にMidjourneyやDALL·E、Fireflyなどの登場により、制作スピードと表現の自由度が飛躍的に向上しました。
画像生成AIの代表的なツール
画像生成AIには多くのツールがありますが、代表的なものとして Midjourney・DALL·E 3・Adobe Firefly の3つが挙げられます。
| Midjourney | 芸術的でリアルな質感表現に強く、クリエイターの間で高い支持を得ています。 |
|---|---|
| DALL-E3(OpenAI) | ChatGPTと連携して自然な文章から画像を生成できる点が特徴です。 |
| Adobe Firefly | 商用利用を前提に設計され、ライセンス面で安心して使えることが評価されています。 |
これらのツールは、デザイン工程を効率化する一方で、生成過程で他者の著作物を参照する場合もあるため、後述の著作権リスクへの理解が欠かせません。
AI画像が急速に普及した背景と社会的インパクト
画像生成AIがここまで急速に普及した理由は、技術進化・環境整備・社会的需要の高まりの3点にあります。
まず、拡散モデル(Diffusion Model)の登場によって、誰でも短い指示文で高品質な画像を生成できるようになりました。
次に、クラウド環境やGPUの進化により、処理コストが大幅に低下したことで、個人でも気軽にAI画像を作れる環境が整ったこともひとつの要因でしょう。
SNSや広告分野では、短期間で大量のビジュアルを制作するニーズが高まる一方で、著作権・倫理・雇用などの課題も浮上しており、社会全体で「AIと創作の境界」を再定義する段階に入っています。
画像生成AIをめぐる著作権問題の全体像
画像生成AIの登場により、「AIが生み出した画像に著作権はあるのか?」という疑問が生まれました。
著作権法は本来、人間の創作活動を保護するために作られた制度。
そのため、AIが自動生成した画像が創作物として扱えるかどうかが議論の焦点になっています。
文化庁をはじめ、各国の著作権当局も見解を公表していますが、まだ制度的な整理は途上です。
ここでは、現状の考え方を整理し、根本的な仕組みを理解していきましょう。
AIが作った画像に著作権は認められるのか
2025年現在、日本の著作権法では、AIが自動的に生成した画像そのものには著作権は認められません。
著作権が成立するためには、「人間による創作的表現」が必要とされています。
つまり、AIが独自に出力した結果は「機械的な生成物」として扱われ、人の創作物とは区別されます。
ただし著作権が発生する場合もある
ユーザーが明確な指示を与えたり、生成結果を修正・編集して独自性を加えた場合は、人の創作性が介在した成果物として著作権が発生する可能性があります。
このように、AI生成画像の著作権の有無は「どこまで人間が関与したか」によって判断されるのが現状です。
著作権法が前提とする「人間の創作性」とAIの違い
著作権法が保護の対象とするのは、「人間の思想や感情を創作的に表現したもの」です。
この「創作性」とは、単なる偶然の結果ではなく、人の意図や個性が反映された表現を指します。
AIの場合、膨大な学習データをもとに統計的な処理を行って結果を生成するため、そこに「感情」や「意図」が存在しません。
そのため、AIが自動生成した画像は、著作権法上の「著作物」とはみなされにくいのが現状です。
文化庁が示す見解と現行制度の課題
文化庁は2023年の「AIと著作権に関する考え方」で、AIが自動生成した画像や文章には著作権は発生しないと明言しています。
理由は、著作権法が保護する対象を「人の思想や感情の表現」と定義しているためです。
AIの出力には人の創作的意図が介在しないため、著作物として扱うことはできません。
ユーザーが生成過程で具体的な指示や編集を行った場合は、人の創作性が加わると判断されるケースもあります。
しかし、AIの関与と人の創作の境界はあいまいで、現行法では明確な基準がありません。
今後は、AI時代に対応した法整備や指針の策定が求められており、文化庁も引き続き議論を進めています。
AIが自律的に生成したコンテンツは、著作権法上の『著作物』には該当しない。
出典:文化庁 - AIと著作権に関する考え方について
著作権侵害が起こる3つの典型パターン
画像生成AIの利用では、単に「AIが作った画像に著作権があるか」だけでなく、他者の権利を侵害してしまうリスクにも注意が必要です。
特に、AIが学習したデータや生成された画像が既存作品を模倣していた場合、知らないうちに著作権侵害が発生することがあります。
ここでは、実際にトラブルが起こりやすい3つの典型パターンを整理し、それぞれの回避ポイントを解説します。
著作権侵害が起こりうるパターン
- 学習データに他者の著作物が含まれているケース
- 生成された画像が既存作品と酷似しているケース
- 商用利用時にライセンス・利用規約を逸脱するケース
学習データに他者の著作物が含まれているケース
画像生成AIは、膨大な画像データを学習して新しい画像を生成します。
その際、学習に使用されたデータの中に他者の著作物が含まれている場合、著作権侵害のリスクが生じる可能性があるため注意してください。
たとえば、インターネット上のイラストや写真を無断で収集・学習したAIモデルが出力する画像には、元の作品の特徴が残る可能性があります。
これは著作権ではなく、「複製権」や「翻案権」の侵害に該当するおそれがあります。
ユーザー自身がそのデータを直接扱っていなくても、AIサービス提供者の学習方法に問題があると、利用者側も責任を問われる可能性があります。
したがって、信頼できる運営元(ライセンス情報を開示しているAIツール)を選ぶことが重要です。
商用利用可能と明記されている画像生成AI
商用利用に向いた画像生成AIツールの候補を、ライセンス情報・商用利用可否の観点から整理してご紹介します。
| Adobe Firefly | Adobe公式に「商用利用が可能」と記載されており、著作権クリアな学習データを用いている旨も公開されています。 |
|---|---|
| DALL·E 3(OpenAI) | OpenAIが「生成された画像の所有権をユーザーに帰属させ、商用利用を許可」しているという情報があります。 |
| Midjourney | 有料プラン加入を条件に商用利用可とされているとの解説があります。 |
| Stable Diffusion(Stability AI) | オープンソースモデルとして、基本的には生成画像を「自由に」商用利用できるという見解あり。ただしモデル・データの取り扱い次第でリスクあり。 |
| Canva AI Image Generator | ビジネス用途(SNS・広告・Web)で使えるとして紹介されており、商用利用可とされるプランあり。 |
生成された画像が既存作品と酷似しているケース
AIが生成した画像が、既存の作品と構図や配色、キャラクターの特徴などで著しく似ている場合、著作権侵害と判断される可能性があります。
これは、AIが学習時に取り込んだデータや、ユーザーが入力したプロンプトによって既存作品の特徴を再現してしまうケースがあるためです。
著作権侵害と判断される可能性のあるプロンプト例
- ブランドやキャラクターの名称を含むもの(ジブリ風など)
- 有名人・実在人物の名前を含むもの(イーロン・マスク風など)
- 有名アーティストの作風を模倣するもの(葛飾北斎風など)
特に、商用利用やクライアントワークでこうした画像を使用すると、権利者からの削除要請や損害賠償請求を受けるリスクが生じます。
類似性が問題となる判断基準は曖昧ですが、他人の著作物を連想させる要素が強い場合は避けるのがいいでしょう。
独自の要素を加える、あるいはAI生成後に人の手で加工・編集を行うなど、創作性を明確にする工夫が必要となってきます。
商用利用時にライセンス・利用規約を逸脱するケース
画像生成AIを商用利用する際に最も注意すべきなのが、ツールごとのライセンスや利用規約を遵守しているかどうかです。
たとえば、Midjourneyでは有料プランに加入しているユーザーのみ商用利用が認められています。
また、Adobe Fireflyのように「商用利用可」と明記されているツールでも、生成画像を再配布・販売する場合には追加条件が課される場合があります。
商用利用を行う前には、各サービスの最新利用規約を確認し、必要に応じて企業内でAI利用ガイドラインを整備しておくことが重要です。
実際に起きた著作権侵害の事例と判例
画像生成AIの急速な普及に伴い、世界各地で著作権侵害をめぐるトラブルが発生しています。
海外では実際に訴訟に発展したケースもあり、日本国内でも相談件数が増加しています。
ここでは、特に注目された3つの代表的な事例を取り上げ、どのような点が問題視されたのかを整理します。
Getty Images vs Stability AI(海外訴訟)
2023年に世界的な写真提供企業 Getty Images は、画像生成AI「Stable Diffusion」を開発した Stability AI を相手取り、著作権侵害で訴訟を起こしました。
Getty Imagesは、自社が保有する数百万点の写真が無断でAIの学習データとして使用されたと主張しています。
さらに、生成画像の中にはGettyのウォーターマーク(透かし)が残っているものも確認され、学習における著作権管理の不備が問題視されました。
この訴訟は現在も進行中で、AIが学習段階で著作物をどのように扱うべきかという国際的な議論の中心となっています。
今後の判決は、AI開発とクリエイティブ業界双方に大きな影響を与えるとみられています。
世界有数のストックフォトサービスを提供するGetty Imagesは、画像生成人工知能(AI)「Stable Diffusion」の開発元であるStability AIが著作権を侵害しているとして米国で提訴した。Getty Imagesが保有する1200万枚以上の画像を許可なく複製し、AIモデルの学習に利用していたという。
出典:CNET JAPAN - ゲッティイメージズ、画像生成AI「Stable Diffusion」開発元を提訴
中国のウルトラマン生成事件
2023年、中国で「ウルトラマン」に酷似した画像を生成AIで作成・販売していた事業者に対し、著作権侵害が認められた判決が出されました。
この事業者は、生成AIを使って既存のキャラクター「ウルトラマン」に似た画像を制作し、SNSやECサイトで販売。
中国の裁判所は、「AIが生成したものであっても、人がそれを利用して既存作品を模倣した場合は著作権侵害にあたる」と判断しました。
この判決は、AIを使った創作でも人の意図が介在すれば法的責任を問えるという重要な先例となりました。
AI生成物であっても、既存キャラクターやブランドの識別要素を利用することは国際的にリスクが高いといえます。
「ウルトラマン」に似た画像提供の生成AI事業者、中国の裁判所が著作権侵害で賠償命令
出典:読売新聞オンライン
日本国内での相談・文化庁対応事例
日本国内でも、画像生成AIに関する著作権トラブルや相談件数が増えています。
文化庁は2023年以降、「AIによる創作物は著作権法上の『著作物』に該当しない」とする立場を明示しつつも、他者の著作物を学習・利用する際の権利侵害リスクに関して、継続的な議論を進めています。
また、弁護士ドットコムや知的財産専門の法律相談サイトには、
- AIが生成した画像を商用利用してよいか
- 他人の作品に似た画像が出てしまった
などの相談が相次いでいます。
現状、日本ではAI生成物に関する明確な裁判例は少ないものの、著作権侵害の可能性があるケースでは、生成した人・利用者の責任が問われる可能性があると言われています。
著作権リスクを避ける5つの対策方法
AI画像を安心して使うためには、ツールや生成プロセスを正しく理解し、著作権侵害を未然に防ぐ運用ルールを整えることが欠かせません。
ここでは、日常的に生成AIを活用するクリエイターや企業担当者が実践できる5つの具体的な対策を紹介します。
これらを意識することで、商用利用時のリスクを最小限に抑え、安全かつ信頼性の高いAI活用が可能になります。
信頼できるAIツールを利用する
AI画像を安全に利用する第一歩は、ライセンス情報を明確に開示している信頼性の高いツールを選ぶことです。
特に商用利用を想定する場合、利用規約に「営利目的での使用が許可されているか」「著作権の帰属が明示されているか」を必ず確認しましょう。
先ほどもあげた通り、代表的なツールでは以下のような違いがあります。
- Adobe Firefly:商用利用可。著作権クリアな学習データのみを使用。
- DALL·E 3:商用利用可。生成画像の権利はユーザーに帰属。
- Midjourney:商用利用は有料プラン加入者のみ可。
- Stable Diffusion:オープンソースで商用利用可だが、学習データに依存するリスクあり。
- Canva AI Image Generator:プランによって商用利用可。
商用利用可とされているツールでも、再配布や販売、特定ブランドの模倣は禁止されている場合があります。
安全に使うためには、「商用可」だけでなく「どの範囲まで許可されているか」を常に確認する意識が重要です。
生成画像の出所・データセットを確認する
AIが生成する画像の品質や法的リスクは、どのようなデータを学習しているかによって大きく変わります。
もし学習データに他人の著作物が無断で含まれている場合、その影響を受けた画像を商用利用すると著作権侵害とみなされるおそれがあります。
そのため、利用するツールがどのようなデータセットを使用しているか、透明性を確保しているかを確認することが重要です。
- ツール公式サイトやドキュメントで「学習データの出所」や「著作権クリアデータ利用」の明記を確認する。
- 学習素材にCreative Commons(CC0など)のライセンスを利用しているかチェックする。
- 不明な場合は、企業や開発者に問い合わせる・FAQを参照する。
- 画像生成後に既存作品と類似しないか、AI類似画像検索などで検証する。
出所が不明なAIモデルを利用すると、ユーザー自身が法的リスクを負う可能性があります。
特に商用案件では、「データの透明性が担保されたツールを選ぶ」ことが安全な運用につながります。
商用利用前に利用規約・ライセンスを確認する
AIツールを使った画像を商用利用する際は、必ず利用規約とライセンス条件を確認することが基本です。
同じ「商用利用可」と書かれていても、その範囲や制限内容はツールによって大きく異なります。
たとえば、SNS投稿や広告利用は可能でも、販売や再配布は禁止されているケースがあります。
- 「商用利用」「営利利用」「再配布」の定義を明確に確認する。
- 画像を販売・納品する場合、クライアント側にもライセンス条件を共有する。
- 生成画像に人物・商標・ブランド要素が含まれる場合は追加の権利確認を行う。
- 利用規約は頻繁に更新されるため、定期的に再確認する。
特に、クライアント案件や広告制作など第三者への提供を伴う利用では、利用範囲を曖昧にせず、契約書にも明記しておくことが重要です。
「商用利用可」という言葉を過信せず、常に最新の規約を確認する習慣を持ちましょう。
既存作品を模倣するプロンプトを避ける
AI画像生成では、「◯◯風」「△△スタイル」などの指示を与えることで特定の作風を再現できますが、これは著作権侵害や商標権侵害のリスクを伴います。
たとえば、「ジブリ風」「ディズニー風」「バンクシー風」などのプロンプトは、特定のアーティストやブランドの表現形式を模倣するため、商用利用時に問題となるおそれがあります。
- 特定の作家・ブランド・キャラクター名を含むプロンプトは避ける。
- 独自の構図・テーマ・雰囲気を言語化して、オリジナルの表現を促す。
- 既存作品を連想させる要素(色調・ポーズ・背景など)も意識的に変える。
- 生成結果が著名作品に似ていないか、出力後に確認する。
AIの生成は統計的なパターン学習に基づくため、特定の作風を再現しようとすると無意識に既存作品に近づく傾向があります。
安全なプロンプト設計=独自性のある指示内容を意識することが、法的リスクを避ける最も確実な方法です。
企業・個人でAI利用ガイドラインを整備する
AI画像を安全に活用するためには、企業や個人単位で明確な利用ガイドラインを設けることが重要です。
ガイドラインを作成することで、著作権・肖像権・商標権などのリスクを事前に回避でき、チーム全体で統一したルールのもと運用できます。
- AIツールの利用目的・範囲・責任の所在を明記する。
- 生成画像の商用利用・再配布に関する判断基準を設定する。
- 著作権侵害や不適切表現を検出するチェックフローを導入する。
- 利用規約の変更や法改正に合わせて定期的に更新する。
- 従業員・外部パートナーにも共有し、教育を行う。
特に企業では、AI生成物の扱いを社内規程や契約書に反映させておくことで、法的リスクやクレーム対応のコストを大幅に削減できます。
個人クリエイターの場合も、作品公開や販売時に「AI利用の有無」を明示するなど、透明性を確保することが信頼につながります。
まとめ|安全に画像生成AIを使いこなすために
画像生成AIは、創作の効率化と表現の幅を大きく広げる一方で、著作権やライセンスの理解を欠くとトラブルにつながるリスクもあります。
これまで解説してきた内容をふまえ、安全にAIを活用するためのポイントを整理します。
- AIが自動生成した画像には原則として著作権が発生しない。
- 商用利用時は、ツールごとの利用規約とライセンスを必ず確認する。
- 学習データの出所や生成結果の類似性にも注意を払う。
- 既存作品やブランドを模倣するプロンプトは避ける。
- 企業・個人でAI利用ガイドラインを整備し、透明性を保つ。
生成AIを使いこなすためには、技術理解と法的リテラシーの両立が欠かせません。
ルールを守りつつ創造性を発揮すれば、AIはクリエイターの強力な味方になります。
今後も制度や技術は進化を続けるため、最新情報を常にアップデートしながら、安心してAIを活用していきましょう。





